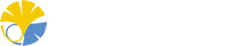● 研究の背景
木星は半径が地球の約11倍と太陽系最大の惑星ですが、固有磁場の強度も地球の約2万倍と強大です。
この固有磁場が太陽風に対してバリアのような役割を果たして形成される木星の磁気圏(※1)も大きさや駆動されるエネルギーの点で太陽系で最大級のものとなっています。
地球と木星の磁気圏の振る舞いの違いを示す一つの例としてオーロラがあります。オーロラは磁気圏に存在するプラズマが何らかのエネルギーを得て磁力線に沿って惑星の極域に降り込んで起こる発光現象です。地球のオーロラは主に太陽風と磁気圏の相互作用に起因する擾乱によって発生するため、常に見られる訳ではありません。
一方、木星の極域では常にオーロラが発生しています。木星の磁気圏には噴火活動を行うイオ衛星(※2)という粒子の供給源があり、磁気圏全体が周期10時間で共回転(※3)していることによって巨大な発電機として化しています。これにより、木星の極域には常に高エネルギーの粒子が降り込み、オーロラの発光としてエネルギーを放出しているのです。
磁気圏に存在するプラズマは基本的には磁力線を横切って移動することがありません。そのため、強い固有磁場を持つ木星磁気圏の中では木星の近傍の領域(内部磁気圏)と遠方の領域(外部磁気圏)との間では粒子やエネルギーのやり取りは非常にゆっくりとしか行われないと考えられてきました。
しかし、ガリレオ探査機(※4)やハッブル宇宙望遠鏡(※5)などによって木星のオーロラや磁気圏の詳細な観測が行われてくる中で、広大な木星磁気圏の広域に渡る連鎖的な変動が数時間から数日という非常に短い時間スケールで発生していることを示唆する観測結果が得られるようになりました。
このような変動を担う、木星の外部磁気圏と内部磁気圏を繋ぐエネルギーの輸送機構の特定が、木星磁気圏の研究における一つのトピックとなっています。
● 今回の研究の成果
ひさき衛星に搭載されたEXCEED観測機は、地球周回から木星のオーロラと、内部磁気圏に存在するイオプラズマトーラス(※6)という構造を2013年の打ち上げから長期に渡って同時連続観測を行っています。今回、ひさき衛星の観測によって、木星のオーロラが3~5日に1回というほぼ一定の頻度で増光しており、増光の後にはイオプラズマトーラスの増光も伴っていることが明らかになりました。また、オーロラの増光とイオプラズマトーラスの増光の時間差が約11時間であることも分かりました。
木星のオーロラの増光は、磁力線に沿って木星の極域に降りこむ電子の数が増えることで発生します。木星のオーロラに関与する高温の電子は主に外部磁気圏に存在するため、増光はそこでの擾乱を反映していると考えられます。一方、イオプラズマトーラスは木星磁気圏の中では比較的内側に存在する構造です。
今回の結果は、磁気圏の外側領域で始まった擾乱がエネルギーの内向きの移動を伴ってイオプラズマトーラスまで広がっていくこと、その時間スケールが約10時間であることを示す証拠です。
● 注釈
※1 磁気圏:惑星の固有磁場によってプラズマの運動が支配される領域。磁気圏の外側は太陽風由来のプラズマが主成分となる。
※2 イオ:木星の衛星の一つ。ガリレオ・ガリレイが手製の望遠鏡で発見したというエピソードが有名。
※3 共回転(きょうかいてん):固有磁場の源である惑星本体が自転することによって、固有磁場に捉われた磁気圏のプラズマも惑星の自転と同じ周期で惑星の周りを回転する現象。
※4 ガリレオ探査機:初めて木星の周回軌道に投入されたNASAの探査機。木星磁気圏のプラズマや電磁場の「その場」観測を行った。
※5 ハッブル宇宙望遠鏡:地球周回から様々な天体を広い波長域に渡って観測するNASAの宇宙望遠鏡。太陽系外の天体の観測が主であるが、時折惑星の観測も行っている。
※6 イオプラズマトーラス:噴火活動の盛んなイオ衛星が放出したガスがプラズマ化し、イオ衛星の周回軌道上にそって円環状に分布した構造。火山から噴出した亜硫酸ガスを起源とする硫黄や酸素のイオンが主成分であり、極端紫外の波長域で発光している。